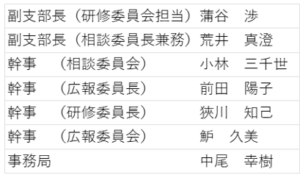突然ですが、「善意の第三者」という言葉を聞いて、みなさんはどのような人物を思い浮かべますか。それも、ただの善意の第三者ではありません。「善意の第三者に対抗することができない」と言われるほどの人です。誰も対抗できない善意の第三者。誰も敵わない立派な人、聖人君子。そのあたりでしょうか。このような人物になるには、相当な努力が必要ですね。ところが法律の世界では、とある条件さえ備えれば誰でも、しかも簡単にこの「善意の第三者」になれるのです。
はじめまして。このたび当欄の執筆を担当することになりました、塚越大介と申します。昨年の3月に開業し、葉山町で小さな事務所を構えております。
さて、われわれ行政書士は法律を専門分野としております。専門分野にはその世界でしか通じない専門用語がありますが、ご多分に漏れず、行政書士が属するこの法律界にもそのようなものが数多くあります。その筆頭格が、冒頭に掲げた「善意の第三者」ではないかと、私は個人的に思っています。そこで今回は、この「善意の第三者」という専門用語を紹介してみようと思います。そして、これを通じて一般の方々が少しでも法律に興味を持っていただければ幸いに思います。
私がこの「善意の第三者」という用語に出会ったのは大学の法学部に入学したときでした。その一般的な意味との違いを知ったときには、法律学の深淵さに身が引き締まる思いがした、などということは一切なく、何やら不思議な世界に足を踏み入れてしまったようで、少し後悔したことを今でも覚えています。
この用語の法律上の意味を知るために、いったいどのような場面で「善意の第三者」が登場するのか、具体例を挙げながらご説明いたしましょう。
Aという人がいました。このAさん、借金をしたのですが、その返済が難しくなってしまいました。このままだと自分の唯一の財産である土地を差し押さえられてしまうと心配していたところ、友人のBさんからこのように持ちかけられました。「その土地を私に売ったことにすれば、差し押さえられなくて済むよ。土地の名義を変えるだけの形式的な手続きにすぎない。土地の所有者はAさんのままだから、これまでどおり住み続けることができる。」
それだけのことで土地を手放さなくて済むならいいかと思い、Aさんは言われたとおり土地の名義をBさんに変更しました。
Aさんはすっかり安心して過ごしていたのですが、ある日、見ず知らずのCさんという人が現れ、こう言いました。「この土地をBさんから買いました。所有者は私なので、すぐに立ち退いてください。」晴天の霹靂とはまさにこのことです。驚いたAさんはこう反論します。「あれはただ名義をBに変えただけで、本当にBに売ったわけではないよ。だから持ち主は私のままだ。」しかし、Cさんは「そんなことは知らない。」と一切聞き入れてくれません。
さて、この事例の中に、くだんの「善意の第三者」が登場します。それはCさんです。Cさんは「第三者」であることは何となく想像がつくと思います。では、どこが「善意」なのでしょうか。聖人君子と思しきエピソードはひとつもありません。
ここが、法律の不思議なところです。法律上、「善意」というのは「善良な心」ということではなく、「本当のことを知らない」という意味なのです。つまり、こういうことです。Cさんは、Bさんが本当に所有者だと思って土地を買いました。AB間の企みを知らなかったわけです。この”知らなかった”という状態こそが、法律上の「善意」なのです。
実際に、民法という法律にこのような条文があります。
(虚偽表示)第94条
第1項 相手方と通じてなした虚偽の意思表示は、無効とする。
第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文も専門用語だらけで分かりにくいですね。ですが、最後のところで「善意の第三者」はしっかり登場しています。
そして、この条文は、まさに先ほどの事例のことを言っているのです。
分かりやすくするために、先ほどの事例に即した言葉に変えてみましょう。「意思表示」とありますが、これは「契約」に置き換えます。「意思表示」と「契約」は厳密には違うものなのですが、今ここでその説明をすると本題から逸れてしまうため、ここでは深入りせず先に進みます。
(ウソの契約)第94条
第1項 AがBと企んでしたウソの売買契約は無効である。だから、土地の所有者はBではなくAである。
第2項 前項ではAとBがした売買契約は無効であるとされている。しかし、Aは本当のことを知らないCには無効であると主張できない。だから、AはCに自分が所有者であるとは言えない。その結果、所有者はCということになる。
「善意の第三者に対抗することができない」というのは、「聖人君子には敵わない」という意味ではなく、「本当のことを知らない第三者には、自分の権利を主張できない」ということなのです。ですから、先ほどの事例でCさんはおそらく、このようにAさんに主張したことでしょう。「私は善意の第三者です。ですからこの土地の所有者は私です。」
自分で自分のことを善意の第三者だと言ってしまう。常識的に考えれば随分と厚かましいことですが、法律界では普通のことなのです。
いかがでしたでしょうか。このようなエピソードは他にいくらでもあるのですが、紙幅の関係で今回はここで終わりにします。
最後にもう一点、法律というものは非常に良くできています。先ほどのケースでは、何も知らずに真面目にお金を払って土地を買ったCさんは、民法の第94条第2項によって土地を無事に手に入れることができました。AさんとBさんはどうなるかというと、Aさんは結局土地を失う羽目になりました。Bさんの末路はさらに深刻です。Bさんは勝手にAさんの土地をCさんに売ったわけです。他人の物を勝手に第三者に売却するという行為は明らかに違法であり、横領罪などで有罪となる可能性があります。さらに、AさんとBさんは土地の名義を偽ったので、二人とも電磁的公正証書原本不実記録罪という罪に問われるおそれがあります。自業自得とはいえ、踏んだり蹴ったりです。
昨今では、いかにズル賢く生きるかが世の中を渡っていくための才覚であるかのように言われることもありますが、法律は決してそのような人のためにあるものではありません。むしろ、真面目に生きている人々の暮らしを守るためにあるものです。先のケースでも、善意で正当に土地を購入したCさんは、民法によって保護されました。一方で、AさんとBさんは、虚偽の名義変更や売買契約を通じて第三者を巻き込んだため、結果として土地を失い、場合によっては刑事責任を問われるおそれがあるという立場になりました。正直者が報われ、ズルをした者が痛い目を見る。法律の根本には、こうした筋が通っているのです。私が、ときに後悔し、ときに挫折しながらも法律の勉強を続けてこられたのは、法律の持つこのような性質に気がついたからです。
みなさんも機会があれば、法律の扉を開いてみてはいかがでしょうか。
塚越大介